2/1_ [Software] セーブしたらすぐLaTeXなスクリプト
普段emacsとxdviの窓を並べてLaTeXで書類を書いているのだが、もう歳なのでlatex-modeで、latex実行コマンドを打つのすら面倒くさくなってきた。もうセーブしたらすぐにlatex実行して、xdviに反映してくれないかなあ。
という訳で、編集しているtexファイルの変更を監視して、変更されたら即latexを実行し、xdviにファイルをリロードするようシグナルを送るというスクリプトをPerlで書いてみたら、50行ぐらいでできた。これでもう、latexやxdviの実行コマンドを憶えておく必要はなくなった。快適、快適。ただ、複数ファイルに分割された文書や、bibtexには対応してないし、latexでエラーが出たときの対処とか全然してないのでもう一工夫必要だなあ。
欲しいという奇特な方はこれ(xdvi-poll.pl)をどうぞ。Debian Linuxでしかテストしてませんのであしからず。しかしこんなのもう誰かやってそうだよなあ。
使い方:
xdvi-poll.pl 編集中のtexファイル
をコマンドラインで実行するだけです。xdviが立ち上がりファイルの監視が始まります。デフォルトではplatexとxdvi-jpを使うことにしてありますが、もし違うコマンドを使いたいときは、
xdvi-poll.pl 編集中のtexファイル latex xdvi
のようにします。ファイルを監視してるだけなのでエディタを選ばないのもミソですね。
2/2_ [SL] おろしや国からも
ロシアからのリンクはこのLinuxフォーラムぽいところでした。読めないですけど。
あとLinuxQuestions.orgとかいうところではSilly applicationsとして紹介されてます。正しい。
2/3_ [花粉症] 目が痒くなってきた
起きたら妙に目が痒かった。そろそろかな、というわけでマスク始めました。ユニ・チャームの超立体マスクというのを使ってますが、これをつけた自分はどう見ても変なおじさんだ。しかし背に腹は変えられぬしなあ。
2/3_ [Software] ウィルスバスターに感染?
トレンドマイクロのウィルスバスター2004の警告ポップアップが文字化けするようになりました。何を警告されてるんだかさっぱり分からんのですが、なんか感染しましたか?でも良く見ると「サ・ケルタフキッスコー」とか「セ・・タフニョ」とかなかなかいい響きだ。

2/4_ [呟き] ぼくは誰?
写真はとある電柱の貼り紙である。
「ぼくの足元におしっこをかけないで下さい」
まではよくある擬人法だが、次の一言で一気に謎の世界へ突入。
「電柱さんがかわいそうです」
え?それを言うキミは誰?「ぼく」は電柱さんではなかったのか?いったい真相はどこに?
謎が謎を呼んでも別に続きはしないのだが。
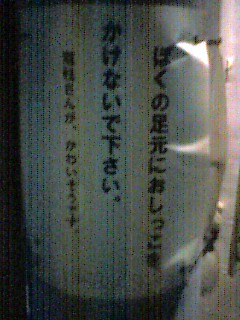
2/6_ [花粉症] 目一時痒ク鼻異常ナシ
自宅近くの林が杉と、今頃気付く間抜けさは、めでたくもありめでたくもなし。
というわけで、今日も起きたときに目が痒かった以外は順調。死刑執行を待つ囚人のような気持ちになる。
2/6_ [テレビ] NHKスペシャル「巨大マネーが東京をねらう」
米不動産投資会社セキュアード・キャピタルの活動をメインにREITの現状を紹介。不良債権となった格安不動産を買い、リフォームして優良テナントをいれ価値を上げたところで転売して利益を得るのが基本。証券化して投資家からの投資を呼び、銀行からの借り入れも組み込んでリターンを増やす。4〜5%の利回りがでるが銀行の貸出金利変動などのリスクもある。紹介されていた会社の金主は、カリフォルニア州公務員退職年金基金のカルパースで、ここから20%(!)の利回りを要求されている。最近は、JREITも立ち上がり不動産価格が高騰。以前より旨みはなくなってきている。今後は地方の不動産も視野に入れるらしい。カルパースは日本で期待している利回りが出なくなればすぐ引き上げると言っている。日本を撤退した後は中国か。
日本の不良債権を回して稼いだお金が回りまわってアメリカの公務員の退職年金になるというのがなんともはや。世界中から儲け話を嗅ぎつけて動いているわけで、アメリカの公務員にとっては頼りになる(?)話だよなあ。日本の年金基金も見習って欲しいもんです。いや見習わなくていいから、せめて無駄遣いは止めてくれないかなあ。JREITも個人投資家にまで利益が回るのかねえ?
2/7_ [論文] Zoltan Gyongyi, Hector Garcia-Molina, Jan Pedersen. Combating Web Spam with TrustRank. VLDB 2004
リンクスパムという手法でGoogleを騙しページランクを上げようとするサイトが多い。手法としては以下のようなものがある。
・密に相互リンクを張りまくる。
・1つのIPアドレスのホストへエイリアスをいくつも作り製品名などをエイリアス名に埋め込む(URL内の文字列にスコアを与える検索エンジンもある)。でそのURLを指すページを山ほど作る。
・掲示板やblogのコメントに、ランクを上げたいサイトへのリンクを張りまくる。
・一見有用なコンテンツを持つページをつくり(UNIXドキュメントのコピーなど)、そこから隠しリンクを対象サイトに張りまくる。それを見て誰かがリンクを張ってくれればランクが上がる(ハニーポットと言うんだそうだ)
この論文では、スパム対策のプロが見て、問題ないと判定されたサイトからスコアを伝播することで、スパマーのサイトへ高いスコアが行かないように工夫したランキング手法を提案している。ページランクの改良版のような趣。ポイントは人間が見ないといけないサイト数をいかに減らすか。スコアを伝播する際にカバーする範囲をできるだけ多くするため、アウトリンク数の多いページを重点的に見ることにしている。そういうページを抽出するために、リンクの向きを逆にしたPageRankを使う。
良いサイトからスパマーサイトへのリンクがあると、スパマーサイトが高いスコアを持ってしまうのが問題だと前半で述べているが、実験した範囲では上位にスパマーサイトはあまり来てないからまあよいんじゃないかと言っている。本当かなあ?
2/9_ [呟き] ゼミで言われたことをそのままやってはいけません
先生や助手の人は、色々な人の面倒を見ているからあなたのやってることを必ずしも深く理解しているとは限らない。したがってゼミではその場の思いつきでコメントをしがち。でも、先生は長年の経験から培われた反射神経でそれらしく聞こえることを言うから要注意。だからゼミで言われたことより正しく面白いことをやって逆に先生を驚かすくらいの心がけで次に挑もう。先生は学生に驚かされることを望んでいる。でも、トンデモになりそうなあなたの研究を軌道修正しようとしてくれているのかもしれないので、よく考え聞き入れるべきは聞き入れること。
追記1:先生や学生として特定の人物を想定している訳ではなく、本当に呟きですのであしからず。
追記2:きっと会社では成り立たない話なのだろうなあ。
追記3:先生が学生のやることをがっちり決めているようなケースでも成り立たないですね。
2/10_ [花粉症] 千葉南部が…
話が違う。なんか今日はポカポカしているではないか。ヘップチンの花粉情報を見たら、千葉南部がすごいことになっている。ああ、とうとう始まってしまったか。東京まで来るのも時間の問題だな。今日はノーマスクで平気だったけど明日からは駄目かもしれん。
そういえば、ヘップチンは今年はimode版をやらないのかな。AIR-EDGE PHONEならOperaでそのまま見えるから問題はないのだが。
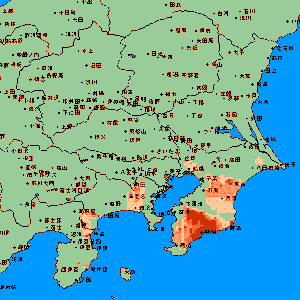
2/11_ [呟き] フーゴ・ハルの絵を実体化したような…
昇降機広間に忽然と現れた異形のオブジェ。同僚のY口君の日記には別方向から撮ったより鮮明な画像がある。作品名も作家名もなく謎は深まるばかり。フーゴ・ハルの絵を髣髴とさせる。うかつに触ると14へ逝かされそうだ。

2/12_ [呟き] 昨日のアレはアスキーアートだったのだけど…
昨日の「YnoY」というエントリは、某店のイニシャルの変形抜き出しであると同時に、ウインクしている牛の顔上半分をアスキーアートにしたものでもあったのだが、気付いた人はいるだろうか?自分ではウマイと思っていたのだけど、ふつー気が付かないよね。でもじっと見てるとだんだんそう見えてきますから。ほら両端のYが角に見えてきませんか?見えてこないですか。そうですか。すみません。
2/12_ [業界] Ask JeevesがBloglinesを買収
登録しただけでほとんど使ってなかったのだが、いつの間にかAsk Jeevesに買収されていたらしい。Ask Jeeves Acquires Bloglines。
で、つらつらと、Bloglines関係情報を眺めていると、なんとモバイル版があって京セラAIR-EDGE PHONEで読むと良いらしい。なんで今まで気が付かなかったのだ。これすごい便利じゃないですか。
2/13_ [開発] Graphviz Hiki プラグインその後
以前、Graphvizをプラグインで組み込んだGraphviz Hikiというのを作った。何人かお客さんが来ているようで、テストページが微妙に編集されていた。需要があるならソースを公開したいところだが、あまりにも実装がアドホックで汚く、環境依存でもあるのがイタイところだ。1ページにいくつもグラフを描けるようにするなど、拡張したいところもまだあるのだが、どうしたものかなあ。
2/13_ [開発] Graphviz Hiki プラグイン公開
と思っていましたが、しばらく遊んでいる暇もないので、ソースを公開することにしました。上記Hikiにダウンロードページを作ってあります。よろしかったらお使い下さい。環境に合わせて書き換えないといけないところがあるのでちょいとややこしいですが。
2/13_ [開発] Graphviz Hiki スクリーンショット
masuiさんのご要望にお答えして。
・Graphvizスクリーンショット「WISSセッションの変遷」
敷居…高いですね。その上何段もありますし。こちらの用意したのを使う場合には、IEにAdobeのSVGビューアをインストールする必要があり、DOTの文法も知らないといけません。自分で運用する場合には、Graphvizのインストールも必要になってきますのでなおさらですね。こっちがGraphvizサーバみたいになればもうちょっと楽になるかもしれませんが。
2/14_ [小物] バッファロー、NASとキャプチャBOXでPCレスTV予約録画「Link de 録!」
おっ、これはPSP用の番組録画にちょうど良いかな。NASとこういうproducer的機能を持った箱の組み合わせってのは他にも色々可能性がありそう。
2/14_ [開発] WYSIWYGでグラフ描きたいですか?
Graphviz Hikiですが、こんなにやる気のないソフトウェアにとみざわさんetoさんから貴重なコメントを頂いてしまいました。ありがとうございます。あれは、当面必要なものを最短手順で実装したらああなったという代物で、時代に逆行しているのは重々承知しております。
さてそこで本題。別に開き直るわけではないのですが、WYSIWYG的エディタでグラフを描くのが人間にとって優しいというのは本当に正しいのでしょうか?私の経験で言いますと、今のところ、十数ノード程度の論文にのっけるようなグラフなら真、数十数百ノードのグラフでは偽です。先だって、300ノード程度のグラフを本からの引き写しで手作りする必要に迫られた私は、色々と手段を模索した結果、GraphvizのDOT形式直書きを選択しました。DOTに慣れるのに少し手間取りましたが、慣れてしまえば後はスイスイ。ノードのつながりだけ書いてコンパイルすればよいだけなので、あんがいあっさり目的を達成することができました。ちょっと我慢して修行すれば素晴らしい効率を達成できるツールの典型といって良いでしょう。萩谷先生言うところの「我慢ユーザインタフェース(GUI)」という奴です。そのへんのお絵かきソフトでは、まずやる気が起きません。やったとしても、死ぬほどの手間と時間がかかったことでしょう。
という訳で私が欲しいのは、ノードの結合情報はテキストでどんどん入力できて、自動でレイアウトをしてくれて、最後にGUIでレイアウトを微調整できるようなグラフエディタです。以前UISTでそれに近いエディタを見たのですが結局公開はされなかった模様です。その後も、理想のエディタは見つけられていません。
数十以上のノードからなるグラフを描く機会など普通ないではないか、との反論もあるでしょうが、大規模なソフトウェア設計図、小説や漫画の登場人物相関図、神話における家系図、ゲームブックのパラグラフ分岐図、「ドラゴン桜」に登場したメモリツリーなどなど、既存のツールでは描きにくい図はたくさんあります。こういった図をサクサク描けるようになって初めてコンピューターは人間の思考をサポートする機械となれるのではないでしょうか。現状ははっきり言ってまだまだですね。
2/16_ [小物] 東芝、ネットワーク連動機能の充実を図ったHDD単体レコーダ「RD-H1」
こ、これは。ミニマルで安くていいかも。
2/17_ [Software] Adobe SVG ViewerのMozilla用プラグイン
知らなかった。迂闊過ぎ。SVG ViewerってMozilla用のプラグインも含まれていたのですね。C:\Program Files\Common Files\Adobe\SVG Viewer 3.0\Plugins\NPSVG3.dllをプラグインディレクトリにコピーしたら動きました。これでMozillaでもGraphviz Hikiを使えるようになりました。
2/20_ [小物] ハンドシュレッダー
ヨドバシでたまたま見つけて購入。アスカという会社のクロスカットハンドシュレッダーCHS193というモノです。恥ずかしながら今日までハンドシュレッダーの存在すら知りませんでした。はがき大の紙をちゃんと縦横にカットしてくれてたったの千円。手回しも味があって、なんでもシュレッドしたくなります。今までATMの明細などは手でちぎって捨ててましたが、これでだいぶん楽になりますな。

2/21_ [携帯] ポケット路線図 for 京ぽん
memn0ckさんのとこで知った、ぷらっと新宿さんの『ポケット路線図 for 京ぽん』をテスト中。すごく細かいのにきっちり読めてすんばらしい。こういうのずっと欲しかったんですよ。見てるだけで楽しくなります。東京地下鉄も見えるようになったらすごく便利そう。
2/22_ [開発] MeCabの挙動
未知語関係の挙動がjumanと異なっている。うーむ。
(1)Let'sは、「Let」,「'」,「s」と3つの未知語に分けられる。カンマ分けの数字(100,000など)も同じ。Jumanは「Let's」で一つの未知語にしてくれていた。これはJumanの方が良かったなあ。
(2)「、」は単独だと「名詞,数」だが、前後があるときにはそれが数字だろうがなんだろうが「記号,句点」になる。うーむ。
しかし細かいことを考え出すときりがないので、適当なところであきらめることにする。(1)はしようがないのであきらめ。(2)については、事前に全角のアルファベット、数字、記号をASCIIに変換しているので、ついでに「、」や「。」を「,」「.」に変換することにした。
2/22_ [Software] Mixiの外部日記仕様変更
なんかここ数日mixiから来る人が減ったなあと思っていたら、こういうこと(あまがささん日記)だったのか。しかも直接外部の日記に飛ばないようにもなったんですな。最近、いかがわしいblogに誘導するようなユーザが出るようになったからその対策なんでしょうなあ。うーん。
2/22_ [呟き] イランで地震、M6.4 280人死亡、被害拡大か - asahi.com : 国際
結構大きかったらしい。早速イギリスが支援を申し出ている。Scotsman.com News - Latest News - Britain Offers Quake Aid
やはり被害は拡大しているらしく見る見るうちに死者の数が増えていく。最新のニュースでは少なくとも420人になっている。Top News Article | Reuters.co.uk
イラン政府は国際救助の必要はないといっているらしい。さてさて。
2/23_ [ゲーム] 5x5の囲碁では白は地を作れない
スラッシュドット ジャパンに、5x5の碁、解かれるなんていう記事が出てました。黒が初手を天元に打てば、白は地を作れないということをコンピュータを使って証明したようです。こんなのとっくに証明されているものと思ってました。
ちなみに1x1はどちらも打てず引き分け、2x2はいろいろあって引き分け、3x3は黒が天元に打って勝ちですが、4x4はどうなってるんだろう?
2/28_ [研究] Internet ArchiveのRecallみたいな
情報処理1月号の記事でInternet ArchiveのRecallをちょこっと紹介した。RecallはInternet Archiveに蓄えられている膨大なウェブページの履歴を全文検索できるサービスで、指定したキーワードの出現数の推移などが分かる面白い検索エンジンだった。「だった」というのは、実はくだんの記事が世に出たときには既にサービスを停止していたのである。ウェブの話はすぐに風化するから困ったものだ。すぐに復活するだろうと思っていたのだが、現在もサービスを停止中で復活の見込みはない。Recallを作っていた人がGoogleに移ってしまったのが大きな原因なのだが、その後を引き継ぐ人は結局現れなかったのかなあ。
前置きが長くなったが、そういうわけで現在、喜連川研のアーカイブでそれっぽいモドキエンジンを作成中である。直接研究にはならないので片手間だが、既に少し動き始めていて色々検索してみるとなかなか面白い。のではあるが、こういうのって普通の人のニーズはあるのかなあ。